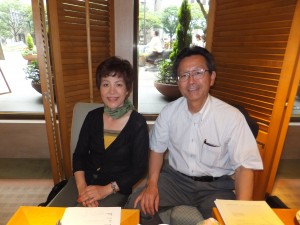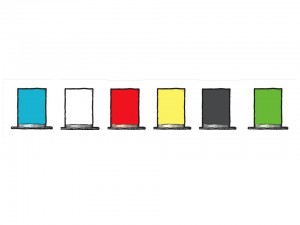今年の我が家の田植えに、セネガルの青年ジャワラくんと中国人女性袁さんの二人の留学生が手伝いにきてくれた。もうかれこれ、3年の付き合いになるが、二人とも好感のもてる若者である。田植え作業では、汚れや辛さを厭わず、黙々とかつキビキビとこなし、徐々に次の作業を想定して動くようになってきた。大変スマートである。そして彼らにとっては新兵器にうつる田植え機に異常な関心を示し、質問し、体験し、この機械のメカニズムを知ろうとする。
今年の我が家の田植えに、セネガルの青年ジャワラくんと中国人女性袁さんの二人の留学生が手伝いにきてくれた。もうかれこれ、3年の付き合いになるが、二人とも好感のもてる若者である。田植え作業では、汚れや辛さを厭わず、黙々とかつキビキビとこなし、徐々に次の作業を想定して動くようになってきた。大変スマートである。そして彼らにとっては新兵器にうつる田植え機に異常な関心を示し、質問し、体験し、この機械のメカニズムを知ろうとする。
田植えが終わり、我が家に戻ると、ジャワラくんが納屋の一角を貸してくれ、と言う。そしてメッカはどっちの方向かと問う。床に紙を敷き、やおらお祈りを始めた。彼はイスラム教徒なのである。肉は食べない、酒は飲まない。国費留学で日本に来ている。あと一年でセネガルに帰り、国家機関で働くか大学の先生になり、日本で学んだことを祖国に活かす、と言う。英語、フランス語、日本語の三か国語が堪能、そして誇りある凛とした態度に彼の将来を確信する。
明治以降日本は、自らを近代国家に作り上げるために西欧文明の急速な搾取を必要とし、その学術研究と教育の最高機関として帝国大学を設置した。更に、その予科教育として1886年(明治19年)高等学校を設置された。この旧制高等学校の教育の理念は「教養」と「愛国心」である。旧制高等学校の定員と帝国大学の定員はほぼ同数、学生は受験勉強ではない勉強で人生を学び、鍛練し、リーダーシップを身につけた。戦前、戦後の日本を創った多くのリーダーは彼らだった。その彼らが世を去り、日本はリーダー不在でさまよい始めた。
日本の若者はこれでいいのか。日本の教育はこれでいいのか。「本学」を修めた、人生観、国家観(世界観)のある凛としたリーダーを育てたい。日本の教育を考えよう。(高原要次)
*7月23日「ラーニング・フォーラム2012」“日本の教育を考えよう”(ゲスト:呉善花氏)