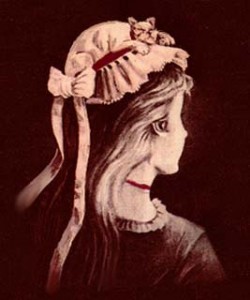こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら
投稿者のアーカイブ
2013年4月 『トップメッセージ』を更新しました。
2013年3月29日 金曜日今月の視点 4月 「LEARNING SHOT」を更新しました。
2013年3月29日 金曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら
2013年4月 “「答えを教えてください」シンドローム”
2013年3月29日 金曜日 “最近の若者は・・・”という表現は、エジプトのパピルスにも書かれているので、太古の昔からの常套句かもしれない。しかし、敢えて言わせてもらうが、“最近の若者は、すぐに答えを教えてもらいたがる、自分で考えようとしない、困ったものだ!”。ビジネスの場面でも、社会生活の場面でも、“何をすればいいですか?”、“どうすればいいですか?”、“言ってもらえばやりますから・・・”と、短絡的に答えを知ろうとする。それを彼らは効率的だと思っている。 この「答えを教えてください」シンドローム(症候群)は、効率的なのではなく、思考することを放棄した、稚拙な問答でしかありえない。
複数の中から自分の責任でどれかを選択する、あるいは独自の案を複数出す、という習慣が乏しい。ある一つのことを他の要素も考えずに行う。上手く行った時はいいが、上手く行かなかった時は、他人のせいにし、時として脆くも砕け散る。人生は、上手く行かないことの方が多く、知らないことばかりなのに。ビジネスは、いつも状況が変化しており、相手の意向に沿わなければ、進まないのに。
カーナビで目的地をセットすれば、自動的にルートを案内してくれて、その場所に連れていってくれる。わからないことがあったら、インターネットで検索すれば、答えを表示してくれる。その答えを切り貼りすれば、一応レポートの体裁は整う。
しかし、人生にナビはない、自分で人生を切り拓くのである。敢えて言えば、自分の人生のナビゲーターは自分である。ビジネスの答えはひとつではない。いくつもの要素を考え、組合せ、予測し、仮説と検証の繰り返しの中で、ベストな答えを自分の責任で選ぶのである。
若者よ、時には、ナビもネットもスマホも使わず、日本の地図を頭に入れて、時刻表を見ながら旅をするのも、いいものだぞ・・・。
ラーニング・システムズ株式会社
代表取締役社長 高原 要次
ラーニング・フォーラム2013開催日が7月1日(月)に決定しました。
2013年2月28日 木曜日ラーニング・フォーラム2013を7月1日(月)「福岡国際会議場」で開催いたします。
詳細は、近日中に公開いたします。皆様のご参加をお待ちしております。
公開講座:テクニカルサービス公開講座を開催いたします。
2013年2月28日 木曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら
鹿児島地区:公開講座「考えをまとめるスキル、説得するスキル」コースを開催いたします。
2013年2月28日 木曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら
鹿児島地区:公開講座「戦略的営業活動」コースを開催いたします。
2013年2月28日 木曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら
今月の視点 3月 「くつろぎの空間」を更新しました
2013年2月28日 木曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら
2013年3月“あかりをつけましょぼんぼりに♪♪”
2013年2月28日 木曜日三月三日は桃の節句。立春過ぎから二月の中旬にかけて飾り、三月三日を楽しみに待つのです。鹿児島の我が家では旧暦によるもので、1ヵ月遅れで飾っていました。そして童謡『うれしいひなまつり』の歌を口ずさむ度に思い出すのが7年前に他界した私の父です。
私は3人姉妹の末っ子。幼い頃、毎年ひな人形を飾りつけしてくれる父の横にちょこんと座り、その一部始終をみている私。とても心地よい思い出です。そして四月三日になると母に着物を着せてもらい「お花をあげましょ桃の花~♪♪」と、3人で適当な振り付けで踊っていたものです。その時の父と母の優しい笑顔は今でも憶えています。今から何十年前の事でしょうか。この時期になると懐かしく思い出します。
父は鉄道員で保線区の仕事をしていました。線路の保守管理を主に行うのが「保線区」です。住まいも鉄道官舎と言って駅などの鉄道関連施設に隣接しており、職員住居用の家でした。目の前をいつも蒸気機関車やディーゼル機関車が通り、私たち家族の交通の足は列車でした。
保線区の責任者であった父はまじめで責任感も強く、台風が襲ってくると真っ先に現場にかけつけたそうです。長女が産まれてまもない頃‘ルース台風’と呼ばれる大変な台風が来た時も、父は線路が気になるものですから家族を残して仕事に出かけ、母は仕方なく一人で胸まで水に浸かりながら赤ん坊を抱えて非難したそうです。
定年退職した父はその後一生懸命勉強をし、‘学校の先生になる!’という念願の夢を果たし、私立高校で土木科を受け持ち教えていました。わからない点も気長に説明し勉強意欲を持たせる教育は生徒さんからも慕われていたようです。そういう姿を小さい頃から見て育った父を母も私たち娘も皆尊敬しています。
大好きな父が亡くなってから母を喜ばせる私たちからのプレゼントは列車での旅です。父や母の生まれ故郷、また母が再度行きたいところを聞き、JR九州の観光列車を利用して温泉宿に連れて行くのです。
列車の旅を喜んでくれる母も、夫(父)を思い出しながら心で会話をしているかもしれません。
(原口佳子)
2013年2月 “部下が変わりますか? 上司が変わりますか?”
2013年1月31日 木曜日あるお客さまに「変わらないのは、上司(管理者)のマネジメント方法ですね・・・。」
と、言われて「ハッ」とした経験がある。変わっていないのは、自分自身のものの見方や接し方だったのではないかと。セミナーの中で は、「自分の考えを押し付けずに、意図を持って部下に問いかける・・・、傾聴が大切・・・」などと言いながら、実際には部下が自分の思い通りに動くように指示を出していることが多かった。さらに、「最近の新入社員の傾向は・・・、平成生まれの若者の言動は・・・、ゆとり・・・」などと口に出している。まさに禁句である。
育成を目的に部下(の言動)を良い方向に変えようとすることは当たり前であるが、部下を変える前にまずは自分自身が変わる、部下に対する見方や接し方を変えることが大切である。マネジメントの方法も世代や場面に応じて変えなければならないのは当然である。
突然ですが、「部下と対話していますか?」
最近は、コミュニケーション手段にメールを活用することも多いが、わざわざ隣の席の人とメールで会話をすることにはかなりの違和感がある。確かに効率的に仕事は進むかもしれないが、直接面と向かった「対話」がない職場では、真意が伝わらずに結果的に生産性を落としてしまうことも考えられる。「対話」とは上司と部下との信頼関係を前提に、お互いの考えやその背景、感情を理解することと言える。部下に一方的に指示するマネジメントが簡単ではあるが、部下の話を聴き、その意図を理解し、「頑張ろう!」という内的動機付けにつなげるためには「対話」によるマネジメントが欠かせないのである。
アメリカのMIT(マサチューセッツ工科大学)教授であるダニエル・キム氏が提唱している「組織の成功循環モデル」がある。我々は結果(成果主義)を重視しがちであり、とくに営業部門では数字を求める。しかし、「結果の質」を問い詰めるだけでは組織は悪循環に陥りやすい。「結果の質」を上げるためには、その手前の「行動の質」を上げることであり、「行動の質」を上げるためには「思考の質」を高める必要がある。「思考の質」は「関係の質」を上げることで高まるという循環である。つまり、「関係の質」(お互いの関係性が良く、認め合っている)を上げることが組織の成功循環を生み出すスタートであり、その手段として「対話」が重要なのである。
世代や場面に応じてマネジメント方法を変える。コーチング、カウンセリング・アプローチ、PDC“F”Aマネジメント・・・、どれも「対話」=コミュニケーションスキルが基本であるが、周りで起きている変化に適応するためにも、上司(管理者)自身のものの見方、接し方が変わり、学び続けることが求められる。
パフォーマンス・コンサルタント 菊池 政司






1-225x300.jpg)