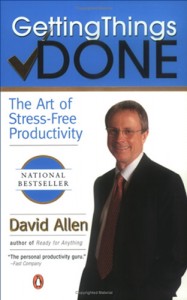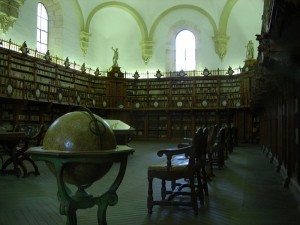仕事を進める上での基本的な考え方に「プライオリティ(優先順位)」という視点がある。ビジネスにおいては、複数の仕事を同時進行で処理していくことが殆どであるが、その際に“緊急度と重要度”で分類し、プライオリティの中で確実に仕事をこなしていく考え方である。但し、次から次へとやらなければならない事が多く出てくると、緊急に振り回され、重要度は高いけれども緊急でないと判断したものは後回しになり、一向に手が付けられないことも多くあるのではないだろうか。この状態からいつまでたっても解放されることがなく、常に色々な事が頭に浮かび、最終的に許容範囲を超えてしまった場合には、ストレスを抱え、集中力を無くし、結果、生産性を落としてしまうことになる。
このような状態を解決するためには大きくは2つのポイントがある。
①「気になる事」を残さず、いかに手軽に整理できるようにするか?
②整理できた状態をどう維持するか?
である。今回はこの2つを実践できるようにし、生産性を高めるための仕事術「GTD®:Getting Things Done」をご紹介したい。
GTD®は、次々起こる案件に追われる、またそれらが頭に思い浮かんでしまい集中すべき事に集中できない状況を改善してくれる画期的な仕事術である。ポイントは、「気になる事」を頭に残さず、一旦頭の外において、いかに集中すべき事に集中できるかである。
「GTDワークフロー」
●収集する: 新たに発生する仕事、気になる事をすべて集める 。
●仕分ける: 行動が必要なものかどうか、どのように行動するかを仕分ける。
●収納する: いつでも行動または処理できるように、整理しておく。
●更新する: 定期的に最新の状態に、収集~収納するまでを行う。
●選択する: 状況、優先順位に合わせて最適な行動・処理を選択する。
私自身もこれまでToDoリストに日々書き出していたが、デイリーや項目単位の書き出しで終わってしまい、“どのように行動するか”まで落とせていないため、未処理の仕事が溜まる傾向があった。GTDワークフローを使って“どのように行動するか”を仕分け、整理することで、気になる事を一旦頭の外に出し、日々のストレスから解放されることが期待できる。
(パフォーマンス・コンサルタント 菊池政司)