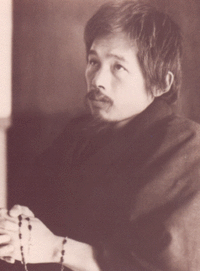こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら
投稿者のアーカイブ
今月の視点 1月 「LEARNING SHOT」を更新しました。
2018年1月1日 月曜日今月の視点 12月 「くつろぎの空間」を更新しました。
2017年12月1日 金曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら
2017年12月 “兄弟のような教授と助教授”
2017年12月1日 金曜日先月、花束贈呈という大役を仰せつかって、大学時代の恩師である岩堀修一先生の傘寿祝賀会および研究室の同窓会に出席してきました。傘寿とは思えないほど若々しく、同級生同士で結婚されたという奥様を同伴されて来られました。お変わりない笑顔が112名出席の会場をあたたかく包んでいました。
学生時代を思い出すとき、頭に浮かぶのは、ふたりの先生の姿です。当時、教授だった大畑徳輔先生と助教授の岩堀修一先生です。栽培技術の改善により、地域農家に貢献することを重視された先生でした。ふたりともとても小柄で、体格も似ていましたし、いつも変わらない笑顔で学生に接してくださいました。一生懸命勉強したというより、楽しみながら研究に没頭し、社会勉強をさせていただいたような気がします。国内外でも実力のある優秀な先生だったと思いますが、私たち学生には、いつも笑顔で優しく指導して下さいました。私が自宅にフランス留学生を迎い入れたのは大畑先生からの依頼でしたし、結婚するときはエンジェルの壁掛けを下さいました。岩堀先生は農場実習や研究で頑張っている学生に、自分のお小遣いでよくご馳走してくださいました。翌日は必ず質素な食事(昼食)をしている姿を拝見していました。
私が入学した当時は、農学部・園芸学科、果樹園芸学でした。現在は農業生産科学科、果樹園芸学と、名称が変わっています。果樹園芸学は、果樹や果物を対象とし、高品質な果物の安定生産・多収を目指して多様な面からアプローチする学問です。鹿児島大学果樹園芸学研究室は、暖地に位置する鹿児島の立地条件を活かして、かんきつ類、パッションフルーツ、アセロラ、アボガド、アーモンドなどの亜熱帯・温帯果樹を主な材料として、幅広いテーマで研究を実施している教室なのです。岩堀先生は2014年、オーストラリアのブリスベンで「ISHSフェロー」を受賞されています。この賞は、園芸科学の分野における世界的に卓越した業績を有する国際園芸学会会員に授与されるもので、岩堀先生の国際園芸学会に対する貢献が評価されたと言えます。
「私たちはとんでもない先生の元で学んでいたんだね!」との声がしきりに会場内で聞こえていました。大畑先生は残念ながら10年ほど前に他界されましたが、奥様とドライブするのが楽しみだと仰る岩堀先生とは、まだまだお会いする機会がありそうです。学生に尊敬された、おふたりの先生方に学ばせていただいた事に感謝です。
今月の視点 11月 「解決への手掛かり」を更新しました。
2017年11月1日 水曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら
2017年11月 GTD®メソッドが生産性を飛躍的に向上させる!
2017年11月1日 水曜日 最初にこのページでGTD(Getting
Things Doneストレスフリーの仕事術)を紹介したのは2014年7月であった。“ストレスから解放され高い生産性を維持する解決策”として、GTD®のワークフローについて説明している。そこから3年が経過し、その間2回ほどGTD®を実践につなげるための方法や長時間労働是正の手掛かりとしてGTDの5ステップを紹介した。
今回再度GTD®を紹介したい理由は「働き方改革」の実現に向けて、企業や個人のGTD®への関心がますます高まっているからである。
先の衆議院選挙で圧倒的勝利を収めた自民党であるが、安倍総理大臣は先般の経済財政諮問会議において、財政健全化と企業に対する社会的要請でもある賃上げ、設備投資に収益を向かわせるよう、“生産性革命”という言葉を使っている。「働き方改革」実現に向けた動きが一段と加速し、そのキーワードの一つが一人ひとりの「生産性向上」であろう。
その生産性向上の方法はAIの導入からシステムの効率化、制度改革も含めて色々あるが、例えば労働時間の管理やタイムマネジメントの徹底、タスク管理の導入に取り組んでも、期待している成果につながるのはなかなか難しいと感じている企業も多いのではないだろうか。
そこで、生産性向上のメソッドとしてGTD®の登場である。
長時間労働は、仕事量が多くいくら仕事をこなしても終わらない、やることが多すぎる、人が足らない等の理由があると思うが、逆にどのくらいの時間がもう少しあればスムーズに片付くのだろうか。実は時間がいくらあったとしても片付かない“人”は片付かない。それは時間が足らないのではなく、頭の中に「スペース」がなくなっていることに原因がある。
「人の頭はアイデアを生むところであって、アイデアを保持するところではありません」とはGTD®の開発者デビット・アレン氏の言葉である。目の前に溜まった仕事をこなしていくだけでも精一杯であるのに、頭の中であれこれ気になることを抱えたままでは、ものごとに集中できず、生産性が上がるどころか逆に効率が下がってしまう。本来やるべきことに納得して集中できる頭の中の「スペース」をいかにつくるかが重要なのである。その「スペース」を作り、維持していくためには、今何があるのか、仕事・プライベートを含め、細かいことから重要なことまですべてを安心・納得できる「仕組み」で把握しておくことである。
GTDでは、生産性向上のメソッドは次の5ステップで管理する。
●把握する: 新たに発生する仕事、気になる事をすべて集めて把握する 。
●見極める: 行動が必要なものかどうか、どのように行動するかを見極める。
●整理する: いつでも行動または処理できるように、整理しておく。
●更新する: 定期的に最新の状態に、収集~収納するまでを行う。
●選択する: 状況、優先順位に合わせて最適な行動・処理を選択する。
まずは、「把握する」が第一歩であるが、簡単に進める方法は、A4の紙を2枚用意するだけでも良い。1枚目は「仕事」、2枚目は「プライベート」に分け、目の前のこと、頭の中で気になっていることをすべて書き出してみる。まだ目の前に現れていなくても今後やらないといけないと、気になっていることすべてである。
次に、書き出したものごと一つ一つについて、簡単に言えば「行動するか、しないか」を「見極める」。「行動を起こす必要があるもの」については、自分が安心できる、大きくは「4つのフォルダ」に「整理する」というシステムを自分自身で管理していくことである。
詳細については、GTD®を体験して頂きたいが、生産性向上、長時間労働の解決にGTD®は間違いなく力を発揮する。
一人ひとりの生産性を上げるメソッドがGTD®である。ものごとに集中する力を高め、一人ひとりの生産性向上が組織全体の“生産性改革”につながっていく。
(パフォーマンス・コンサルタント 菊池政司)
2017年10月 「考える力」
2017年10月2日 月曜日“人間は考える葦である”とは、17世紀のフランスの思想家パスカルのパンセの中の言葉である。「人間は自然のうちで最も弱い葦の一茎にすぎない、だがそれは考える葦である」として、自然において脆弱だが思考する存在としての人間の本質を表現したものである。
「成長」とは、環境の変化に対する正しい適応と定義されるが、この正しい適応とは「考える」そして「選択」し・「行動」して「変化」していくことであろう。人はしっかりと考えることができなければ、成長できない。
この「考える」訓練を「教育」として行うのであるが、学校教育においては、それが十分かどうかは甚だ疑問である。知識として、いわゆる答えのある問いに対して「パターン認識」を学習し、正解を探す「勉強」を行っているように感じる。パターン認識の数を多く覚えた方が、出された問題に対してのヒット率はよくなり、試験の点数はあがる。このパターン認識の学習はそれなりの意味があり、病気の治療や、事故や災害の対策には効果を発揮する。しかし、まったく新しい病気や、500年に1度の災害に対しては、所謂「想定外」ということで解決には至らない。社会においては正解のない問題に対し、そのたびに自分たちが最善と考える答えを出して実行することが求められている。
ではビジネスでは、どのような「考え方」をすればよいのか・・・。そのポイントは3つ。①「根源的にものを考えていく」②「長期的にものを考える」③「多様性を持ってものを考える」である。「根源的にものを考えていく」とは、そもそもの目的に訴求することであり、より本質に迫ることである。トヨタの「なぜ」を5回問う、というのは効果的である。「長期的にものを考える」とは、時間軸を長くし、歴史を知る、その上で未来を予測する。また、将来を見据えて今を変えることである。「多様性をもって考える」とは、複数の視点や立場でものを考えることであるが、自分軸がないとただの紹介コメントになってしまう。この3つのポイントは個別に存在するのではなく、相互に関連しながらその思考を上昇させ、深化させ、前に進める。
更に言えば、「行動」が「考える」前提である。単に机上の思考ではなく、“仮説・検証を繰り返す”、“やってみる”ことで「考える力」は身に付く。
ラーニング・システムズ株式会社
代表取締役社長 高原 要次
今月の視点 10月 「LEARNING SHOT」を更新しました。
2017年10月2日 月曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら
今月の視点 9月 「くつろぎの空間」を更新しました。
2017年9月1日 金曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら
2017年6月 “長崎市名誉市民第1号”
2017年8月29日 火曜日6月、友人2人と久し振りに長崎に1泊で出かけました。特急「かもめ」に乗るのも初めてです。車中でお喋りを楽しみ、市内で観光タクシーを利用する事にした私たちは、「祈りのコース」の案内を頼むことにしました。
長崎平和公園は中学校の修学旅行以来ですから、だいぶ前の記憶しかありません。この日も幾つかの修学旅行生が千羽鶴を「平和の像」に奉納していました。次に、医学博士である永井隆博士の生涯を知る記念館を訪れました。その隣には、亡くなるまでの3年を子供ふたりと過ごした2畳ひと間の家「如己堂」があります。とても小さいです。
永井隆博士は、助教授をつとめる長崎医科大学付属医院で被爆しました。自らも右側頭動脈切断の重傷を負いながら、負傷者の救護や原爆障害の研究に献身的に取り組んだ人です。
彼は放射線医学の研究で被曝し、慢性骨髄性白血病と診断されました。その2ヶ月後に、被爆しています。婦人は自宅で即死だったそうです。それでも永井博士は救済活動(巡回活動)し、私財を投じて子どもたちのための図書館を作りました。病床で文筆活動した彼は、そのなかの「平和の塔」の中で、平和を保つためには現代の世界の人々に掛け値なしの真相を知らせる必要があるとして、長崎最後の日の情景を、ありのまま、少しも飾らず少しも削らず書き綴っているそうです。その後に、ヘレン・ケラー女史が見舞に訪れたり、床についたまま長崎医大で天皇陛下に拝謁したりしています。どんなにか人類愛にみちた人だったかがわかり、胸を打たれます。そして、43歳で亡くなる約1年半前の昭和24年12月26日に‘長崎市名誉市民’の称号を贈られています。
平和公園→永井隆記念館(如己堂)→浦上天主堂→原爆資料館→原爆落下中心地→1本柱鳥居→日本26聖人殉教地へと足を運んだ1日です。
ところで、「平和の像」の顔が、ごく僅か左のほうに向いているのをご存知でしょうか。垂直に高く挙げた右手は原爆の脅威を、水平に伸ばした左手は平和を意味しているのはよく聞きますが、「平和の像」の顔は真正面を向いているのではありません。実は原爆落下中心地に目を向けているのだそうです。タクシーの運転手に像を見て気づく事はありませんかと聞かれた時、私は何故かそのことに気づきました。9割以上の人が気づかないそうです。
「如己愛人(にょこあいじん)~わがいとし子よ 汝の近きものを己の如く愛すべし~」永井氏の言葉ですが、やはり考えさせられます。今回の旅でまたひとり偉大な日本人を再認識出来ました。原爆は広島と長崎に投下されました。現在になって戦争の真実を語り始める方がいらっしゃるそうですね。年老いて、やはり語らなければならない気持ちになられたのでしょう。戦争の悲惨さと平和を訴える活動は、戦争を知らない日本の若者たちだけに伝えるだけでは戦争はなくならないと思います。世界のたくさんの人々にもっと伝え、理解してもらう事が重要である気がします。
(原口佳子)
ラーニング・フォーラム2017 “学びの真髄”開催 ご報告
2017年8月10日 木曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら